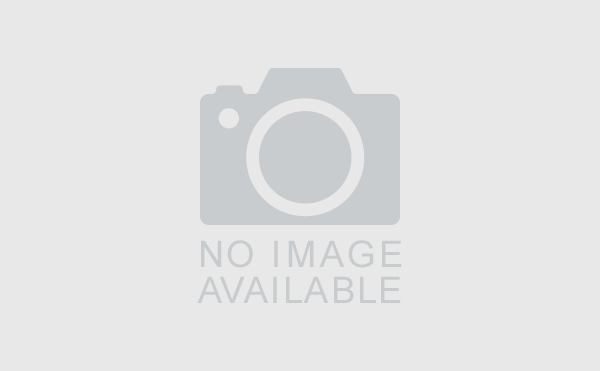さくら2題
さまざまのこと思い出すさくらかな 芭蕉
実質的に2月末で塾を閉めて1か月たつのですが、実はその後このHPがきっかけで
40年以上昔の高校教員時代の生徒と連絡が取れました。
私は一度思い切ると以前のことは一切ふりかえらない、ある意味潔いというか情が
ないというか、さばさばしすぎているとも思うのですが。
彼らとの3年間が私の教師としての原点でした。「教育」が成り立っていた最後の年代
だったのかもしれません。
彼らは非常にエネルギーにあふれていて、到底「学校」という狭い価値観には収まり
切れませんでした。
よくもまあいろいろと問題を引きおこし、そのたびに私はその収拾に追われ、気が付けば
彼らの仲間の一員になっていました。
彼らの一人がよく「先生は何も知らなかった。俺たちがみんな教えてやったんだ。」といって
居ましたがその通りです。
結局管理では人は育たない、人間には「成長していく力」が内在し、それを邪魔することなく
うまく引き出していくのが「教育」だと思うのです。
あの時代は管理教育全盛の時代でしたが、現在管理教育は行われなくなり自主性・個性尊重の
時代になっています。
管理教育はある意味楽ですが、人間の成長を促すものではない。
人間の成長には試行錯誤、失敗がつきものですが、それを許さない制度は人間にとって息苦しい
ばかりです。
ただ「管理されるほうが楽」という生徒は確かに存在し、むしろ多数派を占めると思います。
彼らは『桜井先生、どこに行った?」と探していたらしい。
私は後期高齢者となり、彼らも還暦を超えました。
いずれまた会う機会もあるでしょう。彼らがどのような人生を送ったか楽しみでもあります。
散る桜 残る桜も 散る桜 特攻隊員
特攻隊員が出撃するときに残した句だと記憶しているのですが。
私は教師としては非常に恵まれていたと思います。
生徒に恵まれ、塾を開いてからは生徒にも恵まれましたが、それ以上に講師に恵まれました。
ただ個人塾の経営という観点からすれば、失敗ではないものの成功とはとてもいいがたいものでした。
個人で教育に携わるということは何かしら教育に対する「志」のようなものがあると思うのですが、それと
経営とは相反すると思うのです。
どちらかに重点を置かざるを得ない。
零細な個人塾として生き残るためには徹底して「志」に徹するほかはありません。
それでも受験・教育に対するニーズがあった時代には何とかやってこれましたが、コロナ禍・大学入試
改革による年内入試で一挙にニーズが激減しました。
今業界では寡占化が進んでいますが、どこも新規出店・授業料無料・特待生と大々的な宣伝費でおそらく
中学受験を除いて利益は出ていないのではないかと思います。
またあちらこちらに有象無象のFC個別塾がありますが、どこも生徒はちらほらいるものの到底採算が
取れているとは思えない。
塾が幼児・小学生低学年のお稽古事と同じかそれ以下のレベルにまで落ちてしまっています。
一般の教育に対する認識がその程度のものになっているのでしょう。
それなら私はやらない。
今残っている塾も果たしていつまで持つのか、まったく展望は描けないと思います。