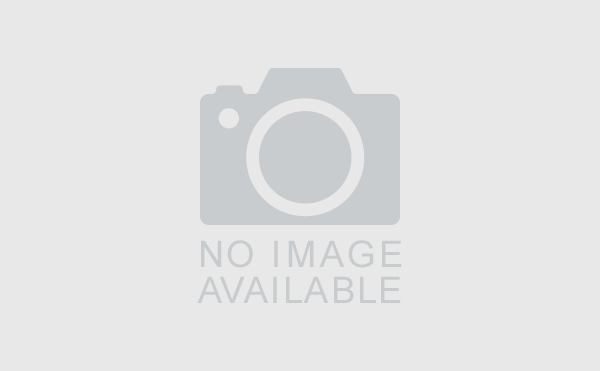今年の受験、補欠合格多数 繰り上げは極めて少数のよう
15日でこのHPを閉じるつもりでしたが、管理者の方のご厚意でブログを続けることにしました。
4月になれば今年の受験がどうだったかはっきりすると思うのですが、今気が付いていることを。
2023・2024入試で定員厳格化が緩んだ。
それ以前は学年ごとに定員1.1倍を超えると補助金カット、2023年以降、大学全体の収容人数の
1.1倍を超えると補助金カットに変更されました。
それでこの2年ほどどこの大学も多めに学生を入学させていた、その帳尻を今年の受験で合わせ
たのだと思います。
おそらくどの大学もぎりぎりの合格者数しか出さず、大量の補欠合格を出した。
以前だと3月の末まで補欠繰り上げがぐるぐる回っていたのですが(特に上智大)、今年は補欠
合格がほとんどないか、ごく少数のみ。
また予備校の合格判定がほぼ役に立たず、昨年の合格最低点を大幅に上回っているのではないかと
思います。
明治大学理工の受験後3人とも「問題が簡単だった。合格したと思う。」と言って帰ってきましたが、
3人とも不合格。
芝浦工大は今まで落としたことはなかったのですが、前期3人受験1人合格、1人補欠、1人不合格。
補欠の生徒が後期受験しましたが、一般受験はまた補欠、共テ利用で何とか合格。
その後二つの補欠の繰り上げは来ていません。
また今年の受験生は教育課程が変わった第一期生ですが、2~3年前の受験生とは手ごたえが変わり
ました。
まずよく勉強します。1日10時間勉強など当たり前。しかも勉強を楽しんでいます。
上昇志向が極めて強い。将来のキャリアをかなり明確に意識している。
そういう生徒がかなりのボリュームで存在していると思います。
今年は共通テストが易化した(英語・国語)の影響で平均点がかなりアップしましたが、それ以上に
上位層で高得点を取った層が分化したと思います。
一つのラインが85%ではないかと思います。
結局生徒の学力を測る一番の物差しは共テの得点率だろうと思います。
このものすごく勉強している国公立大学受験層が私立大の一般受験に流れ込むので、相当な高億点
勝負になったのだろうと思います。
来年以降、この傾向は一層強まると思います。
年内入試組と一般受験組の二極分化、さらに一般受験組の中での二極分化。
これが数年後教育・社会にどういう変化をもたらすか。
大局的に見れば今まで以上の優秀層が出てきていることは明るい面だと思います。
それにしても今年の受験で私大はせめて理科大か明治が欲しかった。国公立でいえば電気通信大か
一橋が欲しかった。
ただあれだけの勉強をさせてきたので、今年の厳しい受験を何とか乗り越えられたのだとも今は思います。